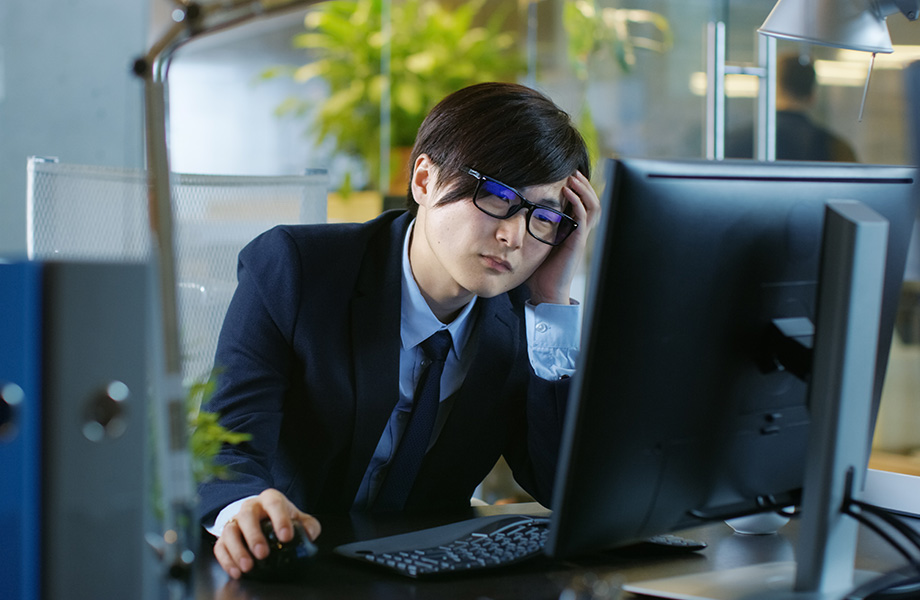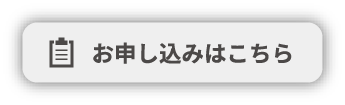情シス用語集 その2

この記事では、情シス(情報システム)に関する用語集をまとめてみました。
用語の意味を理解する上で、ご活用ください。
目次
- セキュリティ用語
- ファイアウォール
- マルウェア
- Emotet
- OSINT
- EDR
- ゼロトラスト
- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)
- IDS
- IPS
- CASB(Cloud Access Security Broker)
- SASE (Secure Access Service Edge)
- サイバー脅威インテリジェンス(Cyber Threat Intelligence: CTI)
- シングルサインオン(Single Sign-On, SSO)
- 脆弱性(Vulnerability)
- ダークウェブ
- DRP(Disaster Recovery Plan)
- DoS攻撃(Denial of Service Attack)
- 二次漏洩
- フィッシング詐欺
- ペネトレーションテスト(Penetration Testing)
- ホワイトハッカー(White Hat Hacker)
セキュリティ用語

ファイアウォール
ファイアウォール(Firewall)とは、コンピュータネットワークを保護するためのセキュリティシステムで、ネットワークの通信を監視し、不正なアクセスを防ぐ役割を果たします。特に、インターネットと内部ネットワークの間に設置されることが多く、許可された通信だけを通過させ、危険な通信をブロックします。
ファイアウォールは、企業や家庭のネットワークを外部の攻撃や不正アクセスから守るために使用されます。
ファイアウォールは、ネットワークセキュリティの重要な一部であり、外部からの不正アクセスを防ぐために非常に有効な手段です。企業のネットワークや個人のデバイスに対して、適切なファイアウォールの導入と管理を行うことで、ネットワークの安全性を大幅に向上させることができます。
マルウェア
マルウェア(Malware)とは、「悪意のあるソフトウェア(Malicious Software)」の略で、コンピュータやネットワークに損害を与えることを目的としたソフトウェアやプログラムの総称です。マルウェアは、データの損失、盗難、コンピュータシステムの損傷、または不正なアクセスを引き起こすことがあります。ユーザーの知らないうちにインストールされたり、意図的に広がったりすることがあります。
マルウェアは、コンピュータやネットワークに重大な影響を与える可能性のある悪意のあるソフトウェアの総称であり、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェアなど、さまざまな種類のマルウェアが存在し、それぞれが異なる方法で拡散し、異なる影響を及ぼします。効果的な対策として、アンチウイルスソフトウェアの導入、定期的なソフトウェアの更新、不審なリンクや添付ファイルの回避、データのバックアップなどが重要です。
Emotet
Emotet(エモテット)は、非常に悪質で高度なマルウェアの一種で、特にサイバー犯罪者によって広く使用されているトロイの木馬型のウイルスです。元々は銀行情報を狙うバンキングトロイの木馬として登場しましたが、時とともにその機能を進化させ、現在では多目的なマルウェアとして、さまざまな犯罪活動に使用されています。
Emotetは、サイバー犯罪者によって広く利用されている非常に危険なマルウェアで、主にフィッシングメールを通じて拡散し、他のマルウェアを配布するために使用されます。感染後、個人情報や機密情報を窃取し、場合によってはランサムウェアを展開するなど、深刻な影響を及ぼします。そのため、企業や個人は、定期的なセキュリティ更新、フィッシングメールに対する警戒、強力なアンチウイルスソフトウェアの導入など、積極的な対策を講じることが求められます。
OSINT
OSINT(Open Source Intelligence)とは、「オープンソース情報収集」を指し、公開されている情報を用いて、インテリジェンス(情報収集)を行う手法のことです。OSINTは、政府機関、企業、研究者、ジャーナリストなどが利用しており、合法的かつ公開されている情報源から得られたデータを基に、分析や意思決定を行います。
OSINTは、公開された情報源から得られる膨大なデータを効果的に収集・分析する手法で、セキュリティ、企業競争分析、調査報道、法執行などさまざまな分野で活用されています。OSINTは合法的でコスト効率が良い一方、情報の信頼性やプライバシーの問題に注意を払う必要があります。適切なツールを使い、情報の正確性と倫理的な側面を考慮しながら活用することが重要です。
EDR
EDR(Endpoint Detection and Response)とは、企業のネットワークに接続されている端末(エンドポイント)に対してセキュリティ監視を行い、サイバー攻撃を早期に検出して対応するためのセキュリティ技術です。EDRは、エンドポイント上で発生するあらゆる疑わしい活動をリアルタイムで検出し、攻撃の兆候を分析・記録して、迅速に対応できるよう支援します。
EDRは、リアルタイムで監視と分析を行い、攻撃の兆候を早期に発見して対応する技術です。高度な脅威検出、インシデント対応、フォレンジック機能を提供し、企業のサイバーセキュリティ戦略において重要な役割を果たします。
ゼロトラスト
ゼロトラスト(Zero Trust)とは、ネットワークセキュリティのモデルであり、「信頼しない、常に検証する」アプローチを基盤にしています。この概念は、もともと企業内ネットワークの境界が分かりづらくなり、従来のセキュリティモデルでは十分に対策ができないことから生まれました。ゼロトラストモデルでは、すべてのユーザーやデバイス、ネットワーク接続を信頼せず、常にアクセス要求に対して厳密な検証と認証を行うことが求められます。
ゼロトラストは、従来の境界型セキュリティの限界を克服し、内部脅威やリモートワーク、クラウド環境にも対応できる強力なセキュリティを提供します。ゼロトラストの導入には多くの技術的な課題もありますが、組織のセキュリティ強化には有効なアプローチといえるでしょう。
ISMS (情報セキュリティマネジメントシステム)
ISMSとは、組織の情報資産を適切に保護するために、情報セキュリティの管理を体系的に実施するためのフレームワークです。ISMSは、情報セキュリティを計画、実施、監視、レビューし、継続的に改善するプロセスを提供し、情報漏洩や不正アクセス、サイバー攻撃などのリスクから情報資産を守ることを目的としています。
ISMSは、組織が情報セキュリティを管理し、維持・改善するための体系的なアプローチです。ISO/IEC 27001に基づいて実施され、リスクマネジメントと継続的な改善を通じて、情報漏洩やサイバー攻撃から情報資産を守ります。情報セキュリティの強化、法規制遵守、顧客信頼の構築など、さまざまな利点があり、企業のセキュリティ戦略において重要な役割を果たします。
IDS
IDS(Intrusion Detection System、侵入検知システム)とは、ネットワークやシステムに対する不正アクセスや攻撃を検出するためのセキュリティツールです。IDSは、組織のネットワークにおける異常な動きや既知の攻撃パターンを監視し、リアルタイムでアラートを発信することによって、セキュリティ侵害の早期発見をサポートします。IDSは、セキュリティインシデントを未然に防ぐための重要な役割を果たします。
IDSを適切に配置することで、早期に不正アクセスや攻撃を発見し、迅速に対応することができます。IDSは、署名ベースと異常ベースの2つの主要な検出方法を使用し、ネットワーク型(NIDS)とホスト型(HIDS)の2つの形態で運用されます。IDSを他のセキュリティ対策と組み合わせて使用することで、より効果的に情報資産を守ることができるはずです。
IPS
IPS(Intrusion Prevention System、侵入防止システム)とは、ネットワークやシステムに対する不正アクセスや攻撃を検出し、それらを自動的に防止するセキュリティシステムです。IDSが攻撃を検出して通知するのに対し、IPSは攻撃をリアルタイムで防止し、ネットワークやシステムへの侵入を未然に防ぐことを目的としています。
IPSは、ネットワークやシステムに対する攻撃をリアルタイムで検出し、防止するための重要なセキュリティ対策です。既知の攻撃パターンの検出や異常な行動の監視を通じて、攻撃を未然に防ぎ、セキュリティ強化に貢献します。IDSとの主な違いは、攻撃を「検出」するだけでなく、それを「防止」できる点です。IPSを適切に運用することで、組織のネットワークやシステムに対するセキュリティを大幅に向上させることができます。
CASB(Cloud Access Security Broker)
CASBとは、クラウドサービスの利用に伴うセキュリティリスクを管理するためのツールまたはソリューションです。企業や組織がクラウドベースのアプリケーションやサービス(SaaS、PaaS、IaaSなど)を使用する際に、セキュリティポリシーの適用、アクセスの監視、データ保護、コンプライアンスの維持などを支援する役割を果たします。
企業がクラウド環境を利用する際に、CASBを導入することで、データの保護、アクセス管理、脅威の検出などの多様なセキュリティ対策を一元的に実施できます。クラウド環境における安全な運用を支援し、企業の情報セキュリティを強化するために不可欠なツールです。
SASE (Secure Access Service Edge)
SASEとは、ネットワークとセキュリティの機能をクラウドベースで統合した新しいアーキテクチャで、企業のネットワークセキュリティとアクセス管理を効率的に提供するためのフレームワークです。SASEは、特に分散したリモートワーク環境や、クラウドサービスを多く使用する企業において重要な役割を果たします。
SASEは、ネットワークのアクセスとセキュリティ機能を統合し、全体的なセキュリティポリシーを中央集権的に管理するため、企業のリソース、アプリケーション、データへのアクセスを保護します。
さらに、クラウドセキュリティ、SD-WAN、ゼロトラストアクセスを統合し、企業のネットワークとセキュリティ機能をクラウドベースで一元管理できるアーキテクチャです。特に、リモートワークやクラウドサービスを多く利用する企業において、ネットワークの効率性とセキュリティを高めるための重要なフレームワークとなります。
サイバー脅威インテリジェンス(Cyber Threat Intelligence: CTI)
サイバー脅威インテリジェンスとは、サイバーセキュリティにおける脅威を特定、分析、評価し、組織がそれに対処するための情報やインサイトを提供するプロセスおよび活動を指します。CTIの目的は、サイバー攻撃者の動向や手法を理解し、それに基づいて予防措置を講じることで、企業や組織のネットワークやシステムを守ることです。
サイバー脅威インテリジェンスは、攻撃者の行動を事前に予測し、攻撃が発生する前に適切な対策を取るための重要な情報を提供します。これにより、サイバー攻撃に対する防御力を強化し、インシデント対応の効率を向上させることができます。
CTIによって攻撃者の動向や手法を理解し、リアルタイムで脅威を把握することで、組織のセキュリティを強化できます。効果的なCTIの導入は、企業がサイバー攻撃に対してより迅速で効果的に対応できるようにし、セキュリティの向上とリスクの軽減を実現します。
シングルサインオン(Single Sign-On, SSO)
シングルサインオンとは、ユーザーが複数の異なるアプリケーションやサービスにアクセスする際に、一度の認証で複数のサービスにログインできる仕組みです。これにより、ユーザーは一度認証情報(ユーザー名とパスワードなど)を入力するだけで、他の関連するシステムやアプリケーションにも自動的にアクセスできるようになります。
ユーザーの利便性向上、セキュリティの強化、システム管理の簡素化を実現しますが、適切なセッション管理や多要素認証など、セキュリティに対する配慮が重要です。
脆弱性(Vulnerability)
脆弱性とは、システム、ネットワーク、ソフトウェア、またはハードウェアに存在する欠陥や弱点のことを指し、これが悪用されることにより、セキュリティ上のリスクや攻撃の原因となります。脆弱性が悪用されると、情報漏洩、システムの不正アクセス、サービス停止(DDoS攻撃)、データ改ざんなどのセキュリティインシデントが発生する可能性があります。
脆弱性は、セキュリティ上の欠陥や不備に関連し、それが攻撃者に利用されると、システムが不正に操作されたり、機密情報が漏洩したりするリスクを引き起こします。
脆弱性管理は、定期的なスキャン、パッチ適用、監視、ユーザー教育などを通じて行われ、セキュリティインシデントを未然に防ぐための重要なプロセスです。また、脆弱性の重大性を評価し、適切に対処することで、組織のセキュリティを強化することができます。
ダークウェブ
ダークウェブ(Dark Web)とは、インターネットの一部であり、特別なソフトウェアを使用しないとアクセスできない、通常の検索エンジンでは見つけられないウェブサイト群を指します。ダークウェブは、通常のウェブ(サーフェスウェブ)やその一部であるディープウェブ(Deep Web)とは異なり、匿名性とセキュリティを重視しているため、合法・違法を問わず様々な活動が行われています。
政治的な自由やプライバシー保護のために利用されることもありますが、違法取引や犯罪の温床となることも多く、アクセス時には慎重な対応が求められます。
DRP(Disaster Recovery Plan)
DRPとは、災害時やシステム障害時に企業の重要なITシステムやデータを迅速に復旧するための計画を指します。これにより、ビジネスの継続性(Business Continuity)が保たれ、ダウンタイムやデータ損失による影響を最小限に抑えることが可能となります。
DRPは、災害リスクの高まりやビジネスのデジタル依存度が高まる中、企業の生命線とも言える重要な戦略です。
DoS攻撃(Denial of Service Attack)
DoS攻撃とは、特定のサーバやネットワーク、システムを対象に膨大なリクエストやデータを送りつけて、そのサービスを過負荷状態に陥らせ、正常な利用者がアクセスできない状態を意図的に引き起こすサイバー攻撃の一種です。
DoS攻撃は技術的な防御手段だけでなく、適切な計画と対応を伴うセキュリティ戦略が必要です。
二次漏洩
二次漏洩とは、一度外部に流出した個人情報や機密情報が、第三者によってさらに拡散・悪用される現象を指します。例えば、企業がサイバー攻撃で顧客情報を流出させた後、その情報が闇市場(ダークウェブ)で売買され、さらに他の犯罪や迷惑行為に利用されるケースが典型です。
二次漏洩は、初期漏洩よりも被害範囲が広がりやすく、影響が長期間続く可能性が高いのが特徴です。そのため、企業や個人は「漏洩を防ぐ対策」と「漏洩後の迅速な対応策」を両立させる必要があります。初期漏洩を防げなくても、情報の暗号化や流出後の適切な対応が二次漏洩の影響を最小限に抑える鍵となります。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺は、信頼できる組織や人物になりすまして、個人情報(パスワード、クレジットカード情報、銀行口座番号など)を盗む詐欺行為です。この詐欺は主に電子メール、SMS、偽のウェブサイト、または電話を通じて行われます。
フィッシング詐欺は年々巧妙化しているため、常に疑いを持ち慎重に対応することが重要です。
ペネトレーションテスト(Penetration Testing)
ペネトレーションテスト(略称:ペンテスト)は、システムやネットワークのセキュリティ脆弱性を発見し、それを攻撃者がどのように悪用できるかを評価するためのテストです。これは「ホワイトハット」ハッカーが実際の攻撃シナリオをシミュレートして行います。
ペネトレーションテストは、現代のセキュリティ対策において欠かせない手法であり、サイバー攻撃への防御を強化するために重要な役割を果たします。
ホワイトハッカー(White Hat Hacker)
ホワイトハッカーは、倫理的に正しい目的で活動するサイバーセキュリティの専門家です。彼らはシステムやネットワークの脆弱性を検出し、それを悪用される前に修正する役割を担っています。別名「エシカルハッカー(Ethical Hacker)」とも呼ばれます。
ホワイトハッカーは、急速に拡大するサイバー脅威に対抗するため、企業や政府機関にとって欠かせない存在です。セキュリティ体制を強化することで、データ漏洩やシステムの破壊といった深刻な被害を防ぐ役割を果たします。
彼らの活動は、デジタル社会の安全性を支える基盤としてますます重要になっています。